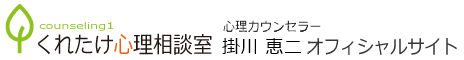チグハグなコミュニケーションでもうまくいく!?
こんにちは。掛川恵二です。
学校や職場、友人関係や家庭内、ビジネスシーンなど様々な場面で、「人との会話がスムーズに気持ちの良いやり取りにしたいなぁ」と思うことはありますでしょうか。
今回は、「コミュニケーションはお互いの勘違いしたまま進んでいくこともある」というお話です。これは、落語好きの友達が「こんにゃく問答」という演目から教えてくれた学びです。古典落語の代表作なのでご存知の方も多いかもしれませんね。
落語が全くの無知な私は初めて知りました。今回のテーマに合わせて簡単にあらすじを紹介します。※多くの噺家が演じていますので、ぜひ一度動画検索をしてご覧になってみてください。
住職不在の荒れ寺が舞台のお噺です。その荒れ寺に旅の僧侶が禅問答(修行僧が質問して和尚が答えるという修行の一つ)を申し入れます。しかし、この大和尚と称する男は無学なこんにゃく屋の主人が袈裟を掛けてなりすまして座っているのです。主人は目が悪く、耳も遠く、話すこともできないフリをしてなんとか追い返してこの場を切り抜けようと試みます。
修行僧が問答を始めますが、大和尚姿のこんにゃく屋の主人は無言を押し通して時折怪しげな表情を浮かべて座っているだけです。
これは、「無言の行(言葉を発せずに精神を集中させる修行のこと)」と勘違いした修行僧。腕を前に伸ばしたり、指を立てて突き出したりと無言で怪しげなジェスチュアを示して和尚に挑みます。
対する偽物和尚も緊張感のある間と力強い身振り手振りで返します。
この無言の怪しげな問答の末、とうとう修行僧が「参りました」と恐れを入って立ち去っていく。
というお噺です。
修行僧は「無言の行」だと勘違いをし、問答に対する和尚の所作を意味深くはかり知れない悟りと受け取り、自身の負けを認めて降参します。
こんにゃく和尚は、この修行僧のジェスチュアから「おたくのこんにゃくが小さい、10丁で300にまけろ」と言ってきたと受け取って、この男は「村の貧しい男」だと判断し、最後には「あっかんべ」の仕草で応戦しカンカンに怒ったとのこと。
コミュニケーションをするときはお互いに、自分の立場や状況、相手の風貌や細かな仕草、その場の雰囲気や間などを勝手に見積もったり判断することがある。お互いに誤解しながらもそれぞれにメッセージを交換し合い、それぞれの解釈でそのコミュニケーションが成立している。
私たちの身の回りでもそんなこともありそうだなと思いました。
お互いに一方的な捉え方をしているためにすれ違って不満や不安に陥っているパターンもあるかもしれませんね。
逆に「恋は勘違いから生まれる」パターンのように、誤解したままの方が円滑な人間関係が築けるということもありそうですね。
誤解や勘違いがあるかもしれないと、普段のコミュニケーションを振り返ってみると新しい発見があるかもしれません。
今回は、落語が趣味の友達から教えてもらった「こんにゃく問答」からコミュニケーションを考察した内容でした。最後までお付き合いいただきありがとうございました。
投稿者プロフィール

最新の記事
 うみ、やま、つち2025年10月22日「自分を大切にしましょう」という言葉の先にあるもの。
うみ、やま、つち2025年10月22日「自分を大切にしましょう」という言葉の先にあるもの。 お知らせ2025年9月29日10月以降のスケジュールについてのお知らせ
お知らせ2025年9月29日10月以降のスケジュールについてのお知らせ 人間関係2025年9月22日チグハグなコミュニケーションでもうまくいく!?
人間関係2025年9月22日チグハグなコミュニケーションでもうまくいく!? お知らせ2025年9月12日秋だ!祭りだ!
お知らせ2025年9月12日秋だ!祭りだ!