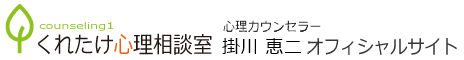自分と向き合う1つの方法
こんにちは。昨日は秋刀魚を美味しくいただきました。掛川恵二です。
前々回の「心はどこにあるのか」というブログはご覧いただけましたでしょうか。今回は、「ヒト以外にも心はあるのか」というテーマで皆さんと一緒に考えていきたいと思います。
心理学、生物学、哲学、医学、科学、様々な学問的な視点で考察されているテーマなので、皆様の中でも1度は考えてみたことがあるのではないでしょうか。
犬や猫などペットを飼われている方であれば、体感的に小動物にも心はあるとお思いでしょう。心をどのように定義するかによっても、何を持って精神活動と呼べるのかによっても捉え方は様々ではありますが、チンパンジー、サル、イルカ、イヌ、カラスなどには喜怒哀楽といった感情や、仲間との別れを悼むといった複雑な感情を示す行動が実際に観察されています。
では、虫や微生物はどうでしょう。いやいや、さすがに無いかなあとも思ったりしますが、苦痛や恐怖の体験から攻撃や防御といった行動に変化が見られるといった研究もあります。
では、では、植物はどうでしょうか。植物は風、湿度、温度など周囲の様々な環境に適応して成長を変化させたりしています。そして、水不足や切断などの強いストレスを受けると「非常に短い超音波」つまり音を発しているという研究結果も示されています。そう考えると何らかの意図を持った応答をしているとも考えることができますね。
では、では、では、、、いよいよ怪しくなってきましたが、「無生物」つまりは石や絵画、服や歯ブラシなど身近なモノたちには心はあるのでしょうか。そのことを考えるにあたり、イギリスの人類学者エドワード・バーネット・タイラーの著書『原始文化』のなかでは「アニミズム」という概念を使って説明をされています。
それは「万物に霊魂が宿っている」という思想です。心理学においてアニミズムは、幼少期に見られる擬人化思考とされており、大人になってからの精神的な健康や自己受容、対人関係スキルに影響する重要な発達過程と位置付けられています。
例えば、ほつれた縫いぐるみに対して「お人形さん痛い?」と語りかけたり、おもちゃを乱暴に扱っている子に対して「積み木さんがかわいそうだよ」と諭したり、自動車に給油する際「ブーブーは喉が渇いたみたいだね」と親が子に伝えたりすることです。
お子さんがいらっしゃらない方であっても、どんなものにも「さん」をつけて呼ぶという場面を経験したことはあるのではないでしょうか。
農作物を育てている方であれば、水やりをしたり肥やしを撒いたりしながら「大きくなってね」「今日も元気そうだ」と話しかけたり、お部屋にサボテンや観葉植物を飾られている方であれば、鑑賞しながらも心の中で愚痴をこぼしたり喜びを報告したり、何か癒しを与えてもらっていることでしょう。
私は幼児の息子が2人おり、畑と植物を育てているので、まさに私の体験談ではありますが。
さて、今回は、「全てのものに心はある。と感じながら過ごす」ことで、日々のお悩みがいくらか和らいでくることを実感していただけるのではないか、と思いブログにしてみました。
お仕事や子育て、家族や友人との人間関係など様々な場面で私も悩みストレスがかかる時があります。そんな時は、現実的で合理的かつ科学的な根拠に基づく解決方法を探ることも大切ですが、幼少期のアニミズム思考のように自然に近い感覚で周囲を見渡してみてはいかがでしょうか。身近なモノに向き合って静かに問いかけたり語りかけたりしながら、ご自身の内側からどんな気持ちや感情が湧いてくるのかをゆったりと感じてみましょう。不思議とお悩みの解決の糸口がご自身の中で見つけられるきっかけになるかもしれません。
美味しい秋の味覚と一緒に自分の気持ちも合わせて味わっていきたいですね。ではまた次回のブログをお楽しみに。最後までお読みいただきありがとうございました。
投稿者プロフィール

最新の記事
 うみ、やま、つち2025年10月22日「自分を大切にしましょう」という言葉の先にあるもの。
うみ、やま、つち2025年10月22日「自分を大切にしましょう」という言葉の先にあるもの。 お知らせ2025年9月29日10月以降のスケジュールについてのお知らせ
お知らせ2025年9月29日10月以降のスケジュールについてのお知らせ 人間関係2025年9月22日チグハグなコミュニケーションでもうまくいく!?
人間関係2025年9月22日チグハグなコミュニケーションでもうまくいく!? お知らせ2025年9月12日秋だ!祭りだ!
お知らせ2025年9月12日秋だ!祭りだ!